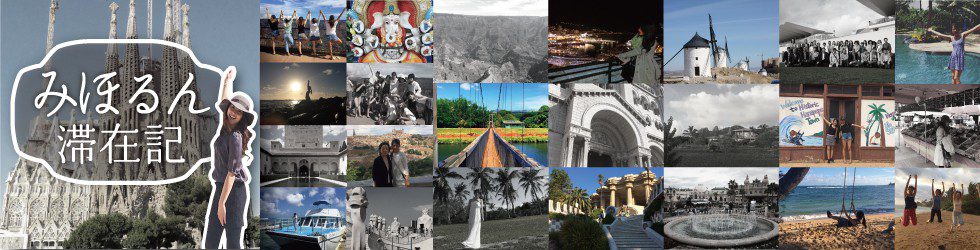皆様、おはようございます。
発言順位1番・中原みほです。
通告に従いまして、
本日「五本松交流拠点施設整備事業」について、町が採用しているPPP(官民連携)方式に関する「プロポーザル」の公正性や、妥当性、また撤退した企業の判断背景、それに伴う今後の見直しの可能性についてお伺い致します。
私はこれまで、町民の皆さまからいただいた率直なご意見、不安や疑問の声を受け、町としての説明責任と、将来にわたって持続可能な行政運営のあり方について、何度も本会議の場で質問を重ねてまいりました。
今回の整備事業に関しましては、「提案企業が1共同体しか出ていないのではないか?」「東京の企業が撤退したと聞いたが、なぜなのか?」「このまま進めて大丈夫なのか?」「町の財政負担はどうなるのか?」等の様々な意見や、ご不安な声が町民の皆さまから多数寄せられております。
PPPという仕組みは、本来「民間の知恵」や「競争原理」を取り入れることで、より質の高い公共サービスを実現し、町の負担を抑えることが期待される制度です。
しかしながら、今回のプロポーザルでは、実際に応募があったのは1共同体のみという結果となりました。PPPの要となる“競争性”や“透明性”が、今回は本当に確保されていたのか。町民の皆さんからも、疑問の声が上がっています。
この仕組みの本来の意義が損なわれてしまえば、制度自体への信頼にも影響します。
現在の状況を踏まえ、「町としてこの状況をどう捉え、どう対応していくのか」が問われていると考えています。
そもそも、この事業が町民の皆さまにとって“本当に必要なもの”なのか。“継続した事業運営が続けられるもの”なのか。今こそ立ち止まって再確認すべき時だと私は考えています。
現状を踏まえ、町として責任ある判断をしていただけるよう、質問いたします。
質問1.今回のプロポーザルでは応募企業が(1者🟰1共同体)にとどまる可能性が高いとされていますが、この状況を町はどのように受け止めているのか。PPP事業の前提である競争性の確保、公平性・透明性の観点から問題はないとお考えなのか、町の見解を伺います。
再質問1−1、今回のプロポーザル応募企業があったのは、先日「1共同体、11事業者からなる共同体」で構成については、設計2社・建設3社・運営6社の計11社、町内4社・町外7社で、1社が代表となって事業を進めていく体制であることのご説明をいただきました。
行政としては「代表企業があるから問題ない」とお考えかもしれませんが、町民の皆様からは、次のような不安な声が多数寄せられています。
「構成が複雑すぎて、誰が責任を負うのか分かりにくい」「11社もいると、1社でも抜ければ全体が崩れるのではないか、船頭多くして船山に上るのでは」といった声です。
前回まで「設計・建設・運営の3社構成」で、それぞれの責任の所在も比較的明確でした。それに対し今回は、顔ぶれも多様で、町民から見れば“寄り合い所帯”的に見えてしまうのも無理はないと思います。そこで伺います。
・仮に1社が途中で離脱した場合、他の企業でカバーできる体制になっているのか?
・意思決定の場では、11社全員が対等に発言するのか?それとも代表企業に一任されるのか?
・それぞれの会社がどこまで責任を持つのか?収益の分配なども、きちんとルールが決まっているのか?
このような運営の仕組みについて、町民にもわかる形で、ぜひ丁寧にご説明いただきたいと思います。町としては「制度上は問題ない」という立場かもしれませんが、町民にとって重要なのは、その制度が本当に持続可能で、万一の際も対応できる設計になっているかどうかという点です。責任体制、意思決定の仕組み、リスク対応、これらについて、町民の不安を払拭できるよう、改めて具体的な説明をお願いいたします。
次の質問に参ります。
質問2.東京の事業者が撤退したとされるが、その背景について町として正式なヒアリング等を行ったのか。撤退理由をどのように受け止め、今後の事業運営にどのように反映させるのか、町の考えを伺います。
再質問2−1、今後の事業運営について、当初から町の構想に関与していたとされる丸善雄松堂は、160年近い歴史を持つ老舗であり、学びの場の運営ノウハウを有する、いわばこの分野のプロフェッショナルです。その丸善が撤退したという事実は、例えるならば、レストランのメインディッシュを作るシェフが抜けてしますようなものであり、施設の核である『学びの場』の中身や信頼性が、空洞化してしまう懸念を覚えます。「学びの場」は文教の町・三股町において、極めて重要な中核機能の一つと認識していますが、その担い手が撤退した事実を町としてどのように捉えておられるのか、見解を伺います。
(現在応募している共同体がその部分をどう担うのかは、まだ町民にとって“見えない”状態に不安)
(丸善雄松堂さんについてですが、「当初から町の構想に関与していたが、今回は応募がなかった」とのことでした。ただ、町民の間では「関与していた=信頼されていた運営の中核的な企業が、なぜ最終的に手を挙げなかったのか?」という点に強い疑問の声が上がっています。私自身も、行政の説明では「応募がなかった」という事実だけが先行してしまい、なぜ彼らが最終的に撤退を選んだのか、その背景がきちんと分析されていないように感じます。たとえば民間の視点で見れば、丸善のような大手が見送ったという事実は、いわば「経営的に合理的でないと判断された可能性が高い」という一つのシグナルです。その企業が「やれない」と判断した背景を、町としてどう受け止めたのか?これは単に「応募がなかった」で済ませるのではなく、将来の事業運営の持続可能性を見直す上でも、しっかりヒアリング・分析を行っておく必要があったのではないでしょうか?このような視点から、改めて再質問させていただきます。)
再質問2―2、今後の事業運営について、企業が利益を追求するのは当然です。私自身、経営者の立場から責任の所在や体制の持続性といった点はどうしてもきになります。特に、大企業ほど経営リスク判断は非常にシビアであるということは、現場の感覚としてよく理解できます。今回の撤退が、「採算が合わない」「先行きが不透明」という理由と考えられるのであれば、本町が提示している運営条件そのものに、構造的な課題があるという警鐘ではないでしょうか?これは企業からの撤退というより、経営的な警告と受け止める必要があるのではないかと感じています。このような観点から、町としてどのように受け止めておられるのか。今後の制度設計やリスク管理にどう反映されるのか、お考えをお聞かせください。
(企業の撤退を『個社の事情』として片付けるのではなく、“システム上のシグナル”として向き合う姿勢が必要です。
今回、質問数が83件も出たということは、制度や条件設計に対する懸念の多さを物語っており、参加は1共同体での11社となりました。行政としては、今後のプレゼンや選定の中で、事業者が制度上どの点をリスクと捉えているのか、その“読み解き”と“改善の余地”をどう把握・反映していくのか、具体的な方針をお示し頂いた理由としてですが、町民の皆さまから届いている、より具体的な声をご紹介しつつ、次の質問に移らせていただきます。)
再質問2―3、今後の事業運営について、町民の皆さんから届いている具体的な声をご紹介します。「運営委託料は5年間で3,250万円、年間にしてわずか650万円。しかも年末年始は休館日なし。週末も休館なしで、朝9時〜夜10時まで開館。職員3名体制を組もうとすれば、どう考えてでも人件費だけで年間2,000万円はかかる。弊社でもこの条件なら絶対に手を挙げません。こうした声を踏まえると、やはり運営モデルの想定そのものが現実離れしていたのではないか?
という疑問の声も無視できません。また一部の方からは、最初は最小限の予算で提示し、足りなければあとから補正を重ねていく、そうした予算膨張型になってしまうのではないか?といった不安の声も聞こえてきています。
そこで伺います。町として、この事業の成否をどう判断していくのか?持続可能かどうかを見極めるための、基準や評価の時期・マイルストーンといったものは設定されているのでしょうか?
仮に、採算性や人件費面で早い段階から赤字が見えてきた場合には、どういった判断がなされるのか?この事業が「持続可能かどうか」をきちんと見極めていく、客観的な評価枠組みがあるのかどうか、改めてお聞かせいただきたいと思います。
このように、採算性の面でも運営体制の面でも、町民からはすでにさまざまな不安の声が上がっています。
そして実際に、丸善雄松堂のような実績ある企業が応募を見送ったことからも、今の条件やスキームのままで本当に大丈夫なのか?という疑問は、より強まっているように思います。
そうした状況を踏まえ、次にお伺いしたいのは
もしこのまま、応募が1共同体(11社)にとどまり、しかも撤退企業の背景もはっきりしないまま事業が進められるようであれば、町としてはどう考えておられるのか?
町民の皆さまにとっては、「本当にこの事業、これで進めてしまっていいの?」という不信感につながりかねないと感じています。
そこで最後に伺います。
再質問2―4、今回の事業について、町としていま一度、立ち止まって見直すという選択肢、たとえば、施設の整備を段階的に行う「スモールスタート」や、状況によっては「撤退」も含めた、より柔軟な対応を検討するお考えはないのか?この点については、町長ご自身のお考えを、ぜひお聞かせいただきたいと思います。
必要に応じて見直しも含め検討”というご答弁でしたが、具体的にはどのタイミングでどのような条件をもって“見直し”に踏み切るのでしょうか?
たとえば、提案内容が極端に不十分であった場合、あるいは唯一の応募グループが辞退した場合、町として“再公募”や“再設計”などの選択肢を排除しないということでよろしいでしょうか?
行政としての“撤退・修正ライン”を持つことが、結果的に町民の不安を軽減することになると考えます。明確なご答弁をお願いします。
私は、今回の五本松交流拠点施設整備事業について、「反対か賛成か」という単純な議論ではなく、“今の三股町に本当に必要な事業か?” “将来にわたって持続可能か?という本質的な部分に問いかけており、むしろ、町の未来にとって本当に意味のある施設となるよう、より良い方向へと導くために、町民の声を代弁しているつもりで、この場に立たせていただいております。
ですが今の段階では、「応募が1共同体でとどまっていること」や「事業構成が見えにくいこと」、そして「当初関わっていた事業者の撤退理由が不透明なまま進もうとしていること」など、懸念が多く残っているのが現実です。
町民の方々が求めているのは、完成予想図ではなく、将来にわたって“本当に持続可能で、町にとって必要とされる施設かどうか”という冷静で現実的な判断であり、町民の声は、単なる不安や批判でもなく、ふるさとを想い、大切な税金の使い道を真剣に考えている声です。
「もう決まったから」ではなく、今だからこそできる判断がある。それを町に強く求め、行政と議会が協力し、町民とともに「より良い三股町」をつくっていく、第一歩にしたいと考えています。
それでは、次の質問に移らせていただきます。
私はこれまで、町内各地の郷土芸能に携わる方々のお話を伺ってきました。
その中で強く感じたのは、「文化を守りたい」という地域の熱意と、それを支える仕組みの“もどかしさ”です。伝統文化は、三股町の誇りであり、地域の一体感を生み、次世代に受け継ぐべき大切な資源です。
しかし、現場では後継者不足、運営資金不足、行政手続きの負担など、深刻な課題が山積となっています。
町として「まちおこしの資源」として掲げるのであれば、現場の声に応じた制度の再設計や支援の見直しが求められるのではないでしょうか。
質問1、現在の補助金制度は、申請や報告書の手続きが煩雑で、文化活動を担う高齢者世代にとって大きな負担となっています。こうした実態を踏まえ、より柔軟な申請・報告制度への見直しや、事後報告型の「助成金」形式への転換など、町民の負担軽減につながる制度改正について、町としてどのようにお考えかお尋ねいたします。
質問2、年間の補助額は 33.000円、公民館助成金を加えても63.000円程度と伺っています。現場では、「昔は祭りの後の「庭もどし」でご祝儀があったが、今は「庭戻し」をしても利益が上がらないため、実施していない」そのため、収入は補助金だけという声もありました。現在は運営が困難との声がきかれています。現場の内容を踏まえ、町として、この金額が果たして妥当なのか。継続的な運営を支えるうえで、増額や新たな支援方法の検討を行う必要ではないかと考えますが、ご見解を伺います。
質問3、文化センターで実施される「芸能発表会」は、郷土芸能団体にとって大きな励みになっていますが、出演の機会が限られ、すべての団体が参加できないという課題があります。町として、各芸能団体が参加できる文化振興の場として、年度当初から町が調整し、複数団体が発表できる仕組みへ検討改善の余地があると考えますがいかがでしょうか?
質問4、担い手不足が深刻化し、地区の人員だけでは編成が困難となり、他地区の協力を得ている団体も見受けられています。こうした現状を町として、どのように受け止めていますか。また、郷土芸能を未来につなげるため、現状の課題をどのように受け止めているのか。さらに、学校教育や地域活動と連携し、こどもたちや若者が主体的に関われるような後継者育成、担い手支援の具体的な取り組みについて、今後の方針をお伺いします。
質問5、現在の郷土芸能保存会補助金交付要綱は、令和7年3月31日で効力を失うとされています。その後の補助金制度の扱いについて、廃止されるのでしょうか?それとも見直しのうえ継続されるのでしょうか?今後の方針について、具体的に伺います。
質問6、町長は、2023年12月の答弁で「郷土芸能は、歴史の産物であるとともに、集落及び町の重要な伝統文化であることから継承していくことが重要であり、郷土芸能は、本町のまちおこし・地域おこしの重要な資源」と述べられました。その立場からと町として、どの団体がどの程度の人員不足なのか、現状を把握されているのか。実際に活動できなくなった芸能や、休止している団体があるが、その解決に関して、町がどのように支援の手を差し伸べようとしているのか改めて町長のお考えをお尋ねします。
郷土芸能は、地域の誇りであり、地域の心そのものだと私は感じています。
太鼓の音、踊りの型、集落ごとの囃子や衣装。どれもが、先人たちの願いや祈り、地域のつながりを今に伝えてくれる、かけがえのない文化財です。
しかし、その担い手である保存会や地元の皆さんは、今、深刻な課題を抱えながら、懸命に伝統を守っておられます。
高齢化や資金難の中で、「続けたくても続けられない」そんな切実な声が、私のもとにも数多く届いています。
行政として、補助制度のあり方や支援の仕組み、次世代への継承体制をいま一度見直し、「文化を守りたい」という現場の熱意と真正面から向き合うことが、これからの三股町に求められているのではないでしょうか。
未来のこどもたちが、地元の芸能を「自分たちの文化だ」と誇れるように。
今日のこの提起が、より良い支援制度づくりと、地域文化の持続的な継承に向けた第一歩となることを願い、私の質問を終わらせていただきます。