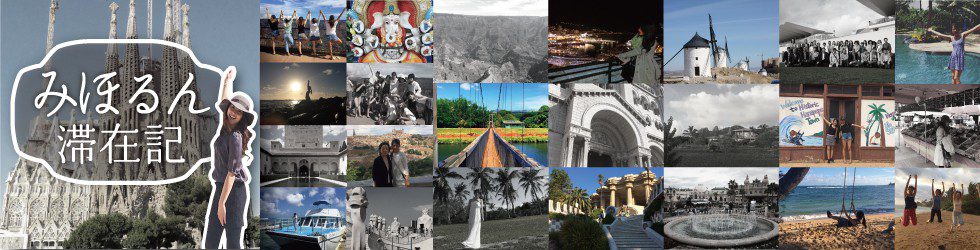🌱【一般質問を終えて】🌱
本日、2025年6月定例会での一般質問を終えました。
「五本松交流拠点施設整備事業」について、町民の声と未来への責任を胸に、11項目にわたり行政に問いかけました。
誰のための施設なのか?今、本当に必要なのか?
町民の声を置き去りにせず、“ともに考え、ともに築く”まちづくりを――。これからも一つひとつ、丁寧に向き合ってまいります。
内容はこちらです↓
2025年6月一般質問内容
皆様こんにちは、
発言順位4番 中原 みほ です。
通告に従い質問させて頂きます。
町長、並びに執行部の皆さまにおかれましては、日頃より町政運営にご尽力いただいておりますことに、心より感謝申し上げます。本質問は、町民の不安や疑問を行政に届ける“声の橋渡し”として、また三股町の持続可能な町づくりを共に考えるための提案であります。
3月の一般質問「五本松交流拠点施設整備事業」について質問を終えた後、私たちは田中議員とともに町民の皆さまへアンケート調査を実施いたしました。318名の回答頂くことが出来ました。町民全体を通して数%ですが、町民1人1人の率直で真剣な声が数多く寄せられました。その内容については資料を配布しておりますので、ぜひご一読いただければと思います。
本日は、こうした町民の声と、今後のまちづくりの方向性を踏まえながら、「五本松交流拠点施設整備事業」について、改めて質問をさせていただきます。
まず、現在の整備事業は、都市再生整備計画事業として補助金も採択されており、PPP方式・指定管理者制度の導入により、着実に進められていることは承知しております。
しかし町民の皆さんからは、「庁舎は古くなっているのに、なぜ交流施設とは別に建てるのか?」「どうせ建てるなら、行政窓口も一緒にして利便性を高めた方がいいのでは?」「そもそも、何のための施設なのかよく分からない」といった不安や疑問の声が多く寄せられています。
また、「三股町中心地ゾーン未来ビジョン」や「みまたん♡ミライカイギ」など、町がこれまで進めてきた住民参加のまちづくりの中でも、「町民と共に考える」「歩いて楽しいまち」「機能の集約と拠点化」がキーワードとして掲げられてきました。
これまでの事を踏まえたとき、現在の五本松整備構想と町民の実感、そして将来の行財政のあり方との間に、少しズレが生じてきているように感じています。
また、庁舎機能との一体化は今からでも検討できないのでしょうか?補助金制度や設計に対して、ある程度の柔軟性があるのであれば、行政窓口や町民課、税務課などの庁舎機能を含めた「複合施設」としての見直しの検討を行うことは。今からでも遅くはないと私は考えます。
では、PPPによる五本松交流拠点施設整備事業における説明責任・管理体制将来見通し適正な運用・今後の体制整備についてお聞きします。質問1、まず初めに、現行の五本松交流拠点施設整備計画について、町の基本的な立ち位置を確認させていただきたいと思います。
この計画は、五本松団地跡地という広大な敷地に、大型の複合施設を整備し、「交流・学び・子育て支援・健康づくり・食・防災」といった多様な機能を集約させるという構想です。にぎわいの創出と同時に、防災拠点としての位置づけもされていることは承知しております。
しかしながら、私たち三股町が今直面している現実を見れば、急速な少子高齢化・人口減少、そして限られた財政基盤という、非常に厳しい状況があることもまた事実です。
先日実施した町民アンケートでは、「税金の無駄遣いにならないか不安」「将来の維持管理費が町の大きな負担になるのではないか」「人口が減る中で、この規模の施設が本当に必要か疑問だ」といった声が数多く寄せられました。特に、Q8. この施設の整備には、現在約7億円(国と町の負担)をはじめ、今後20億円以上の予算が見込まれています。また、維持管理には長期的な町の予算が必要になります。こうした点について、どのように感じられますか?の質問に対しては約40%の方が「維持費など将来の負担が心配である」と回答し、さらに「少子化を踏まえると慎重にすべき」との意見が30%を超えておりました。これは決して軽視できる数字ではなく、町民の多くが「計画を一度立ち止まって見直してほしい」と感じているあらわれだと私は受け止めています。また、「大型の箱モノをつくることが目的化していないか?」「将来空きスペースばかりになるのではないか」といった極めて現実的な懸念の声も寄せられております。そこでお尋ねいたします。町は、コンパクトシティの理念や財政の持続性といった観点から、現行の五本松交流拠点施設整備計画について、再評価・再整理を行う余地があるとお考えでしょうか?
残りの質問は順次行っていきます。
今回の整備では、建設費だけでも20億円を超える大規模な公共投資が見込まれており、それに加えて長期にわたる維持管理費の負担も続いていくことになります。
町民の皆さまからは、「その財源は本当に確保できるのか?」「この施設にかかる費用が、既存施設の維持や教育・福祉予算を圧迫するのではないか?」といった切実なご不安や疑問の声が多数寄せられています。
こうした声を、町としてどのように受け止め、そして将来をどのように見据えておられるのか―そのお考えを町民の皆さまに丁寧に伝えていただくことが、今求められているのではないでしょうか。
それでは次に、「機能や規模の妥当性」について伺ってまいります。
質問2、本事業では、交流機能に加え、子育て支援、健康づくり、そして買い物・食の機能を複合的に導入しようとされています。構想そのものは意欲的で、多世代交流や地域経済の活性化にもつながる可能性を秘めていると私自身も考えております。
しかし一方で、現実として本町は今後さらに少子高齢化・人口減少が進行していきます。このような状況下で、どのくらいの町民が、どのようにこの施設を実際に利用するのか、その具体的な数値や予測が、現時点では明示されていないのが実情です。
実際に町民アンケートでは、
「人口が減っていく中で、施設を作っても活用されなくなるのではないか」
「高齢者しか使わなくなったり、空きスペースが増えたりするのでは」
「もっと具体的に、何人が、どの時間帯に、どの施設を使う想定なのか示してほしい」
といった声が多数寄せられました。利用予測の不透明さが、町民の大きな不安の一つとなっていることは明らかです。
そこでお尋ねします。本町として、将来の利用者数や人口動態の変化を見据えて、必要に応じて段階的に整備する「ステップ方式」や、拡張・縮小がしやすい「スケーラブル設計」の導入について、具体的に検討されたことはあるのでしょうか?
町として、こうした町民の不安や疑念にどう応えるのか――その姿勢が今まさに問われています。未来を見据えた柔軟な施設計画こそが、町民にとって「安心して長く利用できる場所」となるはずです。その意味でも、ステップ方式やスケーラブル設計といった柔軟性のある整備方針を真剣にご検討いただき、明確な説明と丁寧な情報公開をお願い申し上げます。
それでは次に、質問3に移らせていただきます。
(質問3)五本松という立地の適正性についてお尋ねいたします。本事業では、五本松団地跡地を活用し、大規模な交流拠点施設を整備するという構想が進められております。町からの説明では、「将来的なまちづくりの拠点に適している」「中心市街地とは適度な距離があり、防災拠点としても有効である」といった評価がなされています。
しかし、実際に町民アンケートや自由記述には、次のような声が数多く寄せられております。
「災害時に本当に避難拠点として機能するのか不安」「病院や学校が近くにない。高齢者や子育て世帯にとっては使いづらい」など、立地の選定そのものに対する不安や疑問が非常に強く表れております。このような声を受け止めた上で、五本松という立地に、防災・交通・観光・医療・教育の観点から適正配置であるとの判断根拠を示せるのでしょうか?
回答後(三股町交流拠点施設整備事業 令和3年度基本計画 10・11ページ)
防災面で、五本松が災害時の拠点として適しているという判断は、どのような災害リスク評価に基づいてなされたのでしょうか?特に南海トラフ地震や豪雨、土砂災害、津波など、さまざまな自然災害に対する想定に基づき、安全性や避難導線、周辺避難所との役割分担等をどのように検討されているのか、客観的なデータやシミュレーションなどがあったのでしょうか?
交通アクセスの観点で、現在のバス路線網や公共交通の現状を踏まえ、自家用車を持たない高齢者や子育て世帯が、どのようにこの施設を利用する前提になっているのでしょうか?特に、バスの本数や運行時間、最寄りバス停からの徒歩距離など、具体的なデータを基に「通いやすさ」の裏付けがなされているのか、お答えください。あわせて、駐車場の収容台数、自転車置き場、将来的な乗合タクシーやカーシェアなどの検討も含めて、利便性確保に向けた考え方をお伺いします。
医療・教育施設との位置関係で、医療機関との距離やアクセスに関しては、特に高齢者や緊急時の対応を考える上で極めて重要です。万一の災害時に搬送が必要になった場合、現場からの移動に支障はないのか。また、平常時における保健機能・健康づくり機能をどう結びつけるのか、その導線は確保されているのでしょうか?
教育面で、近隣に小中学校がない中で、子どもたちや子育て家庭が利用するための送迎・連携体制などはどのように設計されるのでしょうか?
放課後の学びの場として活用するビジョンがあるのであれば、学校・教育委員会との調整の有無や内容を具体的に教えてください。
(質問4)では次の質問に入ります。町民参加のプロセスについてお尋ねいたします。本事業「五本松交流拠点施設整備事業」は、すでに本議会でも議決を経て進行中であることは承知しております。
しかし、現在の進捗状況を踏まえても、まだ施設の配置・規模・機能の詳細については確定しておらず、住民への共有や説明が十分に行き届いていないとの印象を、私は強く受けております。
住民アンケートでも以下のような声が多く寄せられております。「説明会が1回だけでは理解できなかった」「“多機能施設”といっても、中身のイメージがまったく湧かない」「町民の意見をもっと聞いて反映させてほしい」「ワークショップをもっと開いて、実際に図面や模型を見ながら話したい」「将来の利用者としてまったく実感が持てない」といった声がありました。このように、町民の多くが本事業の具体的なイメージをつかみ切れていない状況にある中で、今後の設計段階で、町民との対話をどのように担保していくのかは非常に重要なテーマだと考えます。そこでお伺い致します。可決されたとはいえ、具体的な配置・規模・機能が固まる前に、町民への再意見聴取やワークショップの開催を検討すべきではないでしょうか?
本来、このような複合施設の整備には、住民一人ひとりが「これは自分たちの暮らしにどう役立つのか」「どのように使用できるのか」という具体的な納得と共感が必要不可欠です。町民の皆様の期待と不安が交錯する中、丁寧で双方向的なプロセスこそが、将来にわたって誇れる施設づくりに繋がると、私は信じております。どうか町として、このプロセスを大切にする姿勢を、今回の設計段階でも明確にお示し頂きたいと感じております。よろしくお願い申し上げます。
次の質問に参ります。(質問5)次に、説明責任の在り方と情報公開のあり方について伺います。五本松交流拠点施設整備事業は、単年度で完結するような短期の施策ではなく、建設から管理・運営まで含めて① 本事業の財務構造や維持管理費を含めた長期的な支出見通しを、町として事前に公表することはできないのでしょうか?
可能であれば、どのタイミングで、どの媒体(町広報・HPなど)で公表予定か、具体的にお示しください。一方、もし現時点で公表が難しいという判断であれば、その理由についても「事業者との協議中」「入札等の影響がある」などの事情を含めて、明確にご説明いただきたいと思います。② 次に、KPI(効果検証指標)の設定と事前公表についてです。この施設が、投資に見合った成果を生むかどうかを測定するためには、「効果指標の可視化」が不可欠です。たとえば、年間利用者数の目標(年代別など)、災害時の避難対応訓練回数や収容可能人数、テナント事業の収支・稼働率、町民満足度調査など、複数のKPIを明確に設定し、定期的に評価していく仕組みが求められると考えます。なぜ事前公開はできないのでしょうか?町として、すでに検討中のKPIがあるのであれば、その具体的項目・目標値・評価スケジュールを示してください。まだ未確定である場合には、いつ頃までに策定・公表するのか、その見通しを明確にお示しください。③ 最後に、計画の全体像が十分に示されていない段階で、なぜ設計や事業者募集を先行して進めようとされるのでしょうか?本来、施設の理念・構成・収支構造・住民理解がある程度整ってから事業者を募集し、設計を進めるのが順序であると思います。 順序を得ず、なぜ町は「設計・事業者を先に選定し、内容を固めていく」という方式を取っているのでしょうか?「スケジュールありき」なのでしょうか?「制度上、先に動かざるを得ない事情」があるのでしょうか?「基本構想の範囲内で問題ない」という判断であるのですか?その背景と根拠を、できるだけ具体的にご説明いただければと思います。
住民説明資料に、「KPIと財政見通しを図表化して明示する」ことの義務化をして頂けたらと思いますし、説明責任と情報公開が伴わなければ、どんなに立派な設計や建物でも、町民にとっては“他人ごと”で終わってしまいます。ぜひ、こうした町民の声に誠実に受け止め、向き合いながら、開かれた行政運営を行っていただきたいと、心からお願い申し上げます。
次の質問にうつります。(質問6)本事業にかかる財政負担について、町民の間では非常に高い関心と不安が寄せられております。まず、建設費や設備費、外構費、設計監理費などを合わせたイニシャルコストだけでも、概ね30〜35億円規模と見込まれるとおもいます。さらに、維持管理費を含むランニングコストは、毎年およそ1億円前後と試算され、30年間のスパンで見ると、総事業費は50〜60億円規模に膨らむと考えられるのではないでしょうか。
アンケート自由記述欄にも「20億円以上の追加負担は重すぎる」「年金生活の中で、これ以上税負担が増えることは避けてほしい」という切実な声が多数見られました。そこでお尋ねいたします。本事業の30年スパンでの財政影響(イニシャル+ランニング)の見通し、町の総合計画との整合性についてご見解をお聞かせください。
次に、町の第6期総合計画や関連政策で掲げている方針――たとえば「コンパクトなまちづくり」や「公共施設の統合・複合化」、「財政健全化」といった理念に対して、町民からは「まず既存施設の統廃合や老朽施設の整理を優先すべきではないか」との声が多く寄せられており、方針との矛盾が生じていないかを再確認する必要があり、本事業がどのように整合しているのかについてもお伺いします。
本事業は、三股町の将来にわたり長期的な財政影響を与える可能性がある重要な投資であるからこそ、町民一人ひとりが「本当に必要な施設なのか」「町の将来像に合致しているのか」を判断できるだけの材料が必要です。
計画の正当性や持続可能性を町民に納得してもらうためには、財政見通しとまちづくり方針との整合性を、数値や戦略とともに丁寧に示すことが不可欠です。
どうか、町民の目線に立ち、将来世代にも責任を持てる説明をお願い申し上げます。
質問7、本事業においては、現在「都市再生整備計画事業」の補助制度が採択されており、設計・建設・運営を一体化したDBO方式の導入が進められております。一方で、町民からは「庁舎機能を一部移して、補助をもっと有効に使えないのか」「そもそも庁舎との一体整備を補助対象にできるのではないか」といった意見や疑問が多く寄せられています。実際にアンケートでも、「別棟で建てるより一体型のほうがコスト面でも現実的」「他の市町村では庁舎を含んだ施設で補助を受けている例もあるのでは?」といった指摘が見受けられました。そこで、お尋ねします。現在採択されている補助制度において、庁舎機能の一部導入が制度上あるいは実務上、
質問8、現在、五本松に整備が予定されている交流拠点施設は、町民交流の場や子育て支援、保健相談、マルシェ機能など、多様な機能を持つ複合施設として構想が進められていると伺っております。
私たちが実施した町民アンケートでも、「子育て支援や保健、社会福祉協議会などとあわせて、行政窓口も一箇所に集約してほしい」「複数の施設を行ったり来たりするのが大変だ」「高齢者や障がいのある方、小さなお子さん連れの家庭にとっては移動が大きな負担だ」といった、非常に切実な声が数多く寄せられました。こうした町民の実感に対して、町としてどのように応えていくのか、今まさに問われていると感じております。そこで、お尋ねします。現在の設計計画を活かしたうえで、行政窓口を含む「庁舎機能との複合型施設」への転換が検討可能なのでしょうか?
交流拠点施設は町の未来の象徴的な公共空間であり、機能面・経済面・心理面いずれをとっても、「分ける」より「まとめる」方が合理的という判断が成り立つならば、いま一度立ち止まって検討することは、決して遅すぎることではないと思います。
町民の利便性、職員の働きやすさ、財政的合理性のすべてを視野に入れた、柔軟かつ前向きなご答弁を、町長または担当課長よりお願い申し上げます。
質問9、五本松交流拠点施設整備事業は、現在基本設計を終え、いよいよ実施設計段階に入ろうとしていると伺っております。そうしたなか、町民アンケートでは、「庁舎機能と交流機能を一体化すれば、光熱費や維持管理費の削減につながるのではないか」「職員間の連携がスムーズになり、事務の効率化が図れる」「住民が複数の窓口を一度に回れるようになり、利便性が大きく向上する」といった非常に具体的な意見が多数寄せられています。
特にQ6、Q10において、「一体化による効果をなぜ検証しないのか」「検証の上でベストな配置を選ぶべきだ」というご指摘が目立ちました。
そこで、以下の観点から町の考えをお伺いしたいと思います。
第一に、「運営効率の向上」についてです。
一体型施設とすることで、光熱費や警備・清掃等の委託費、設備保守管理費などが一元化され、ランニングコストの削減が期待されます。
たとえば複数棟にわたる管理よりも、1棟に統合した方が、エネルギー効率や契約単位の集約が可能となり、管理コストが10〜20%縮減されるという報告も他自治体にはございます。
本町としては、このような一体型施設にすることで得られる運営面の数値的効果について、シミュレーションや費用対効果の比較検証を実施されたのでしょうか?
第二に、「職員の動線と業務効率」についてです。
複数の庁舎や拠点に分散して配置されてしまえば、職員同士の連携に時間的・人的ロスが生じます。
とりわけ高齢化社会では福祉課・町民課・税務課の連携や、子育て支援と保健業務の連携といったクロスセクションの対応が求められる場面が多くなると予想されます。
同一棟内に業務が集約されていることにより、職員間の連携がどれだけ迅速になるのか、事務処理にかかる時間や残業時間の削減効果などの定量的な検討が行われているのか。
第三に、「住民利便性の最大化」についてです。
複数の施設に分散している場合、たとえば高齢者が証明書を取りに役場へ行き、その後子や孫の保育支援で別施設に移動、健康相談でまた別の庁舎へ行かなければならないという事例が実際にあると聞いております。
一体化されていれば、徒歩数分の移動で複数の行政サービスを完結できるワンストップ化が可能となり、時間的・心理的な負担が大きく軽減されます。
こうした住民目線の導線について、モデルケースやユーザー視点のシミュレーションなどを活用した検証を今後実施設計段階で行うご予定はあるのか。
以上を踏まえまして、改めて町にお伺いします。
最終設計段階において、庁舎機能と交流機能を一体化することによる運営効率の向上、職員導線の最適化、住民利便性の最大化について、数値的な検証も含めて再度見直す考えがあるのかどうか、ご答弁をお願い申し上げます。
(質問10)庁舎機能と交流機能を「別々に整備した場合」と「一体型施設で整備した場合」のイニシャルコストおよび維持管理コストの比較分析は行われたのでしょうか?仮に別棟整備をした場合には、それぞれにかかる建設費、外構・駐車場整備費、ランニングコストとしての光熱費、清掃・警備費、将来的な大規模改修費や設備更新費など、二重にかかる項目が多くなる可能性があります。庁舎機能と交流機能を別々に整備した場合の費用・維持管理コストと、現行の一体型との比較分析を実施したのでしょうか?
質問11、本町にはすでに、「元気の杜」「文化会館」「中央公民館」「健康管理センター」など、多種多様な公共施設が点在しております。
そのような中で、現在進められている五本松交流拠点施設の整備計画は、それら既存施設と機能が重複するのではないかという懸念が、町民から多く寄せられております。実際、アンケートの自由記述欄にも、「既存施設をもっと有効活用すべきではないか」「新しい箱ものを作る前に、今ある施設の老朽化対策を優先してほしい」「文化会館や元気の杜をどうするのかも含めて説明してほしい」といった率直な意見が多数挙がっております。そこでまずお伺いします。既存施設との機能分担・再編・再利用について、町としてどのように検討されているのでしょうか?
「元気の杜での保健・健康づくり事業と、五本松の健康支援機能が重複する場合、どちらに軸足を置いていくのか」といった具体的な整理方針や再編戦略の有無を明確にご説明ください。
私は本事業そのものを否定するものではありません。むしろ、三股町が未来に向けて「町民の暮らしを支える拠点」をつくろうとされているその趣旨には、大いに共感しております。
ただ、その実現プロセスにおいて、いま町民が感じている不安や疑問、「本当に必要な計画なのか」「財政的に持続可能か」「町民の声がどこまで反映されるのか」こうした根本的な問いに、行政として真摯に向き合っていただきたいと強く願っております。
特に、まちづくりにおいて「住民参加プロセスを重視する」という理念を掲げながら、設計や議論の段階で多くの町民が置き去りにされていると感じるのであれば、そのギャップを埋めることが、私たち議会・行政の責務であると考えます。
どうか、今後の設計・運営段階においても町民一人ひとりの声に丁寧に耳を傾け、「ともに考え、ともに築く」姿勢を大切にしていただきたく、心よりお願い申し上げます。
最後になりますが、本質問を通じて、町長ご自身のお考えとともに、町民と向き合うまちづくりの未来像について、ぜひお聞かせいただければと存じます。
今後も、町長並びに執行部の皆さまには、明確な方針と時代に即した先進的な行政運営をお願い申し上げ、私の一般質問を終わらせていただきます。